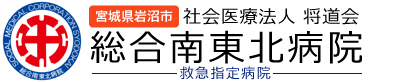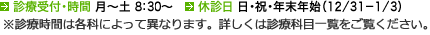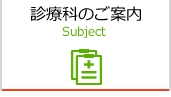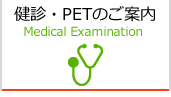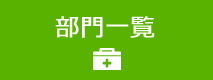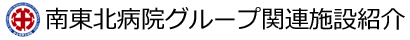薬剤科だより
保湿剤について
薬剤科 薬剤師 緑山 莉枝
乾燥が気になる季節になってきました。マスクを日常的に付けるようになって肌荒れに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。今回は保湿剤について紹介します。
保湿剤の効果
保湿剤には大きく分けて
①皮膚表面に被膜を作り、潤いを保持する効果 例)ワセリン
②保湿剤に含まれる水分と結合する成分が、角質層内で水分保持を行う効果
例)尿素製剤、ヘパリン類似物質、セラミド、ヒアルロン酸、ビタミンA・E
以上2種類の効果があります。
保湿剤の選び方
保湿剤の選び方は基剤と有効成分の2つを見ると良いとされています。
① 基剤
| 軟膏 | 皮膚保護作用があり刺激が少ないです。しかし、塗った際にべとつくことがあります。 |
| クリーム | 軟膏と比べるとべとつきが少なく塗りやすいです。水で洗い流すことができます。 |
| ローション | さらっとしていてよく伸びるため、摩擦が少ないです。 |

この中でも特に床ずれの原因となるドライスキン(皮膚の角層と呼ばれる部分の水分量が低下して、肌が乾燥した状態)の予防には、塗った際の摩擦が少ない低刺激性のローション剤を選び1日2回ほど使うと良いとされています。
② 有効成分
| ワセリン | 安価で手に入りやすく刺激感が少ないです。入浴後に使用すると特に効果があります。 |
| 尿素製剤 | 角質を溶かす作用がありまずが、刺激感もあります。 |
| ヘパリン類似物質 | 持続的な保湿効果と血行促進効果があります。また、基剤は軟膏やクリームなど様々なタイプがあります。 |
上記の有効成分以外にもセラミドやヒアルロン酸・ビタミンなどがあります。
これらの成分が含まれているものは医療用医薬品だけではなく、市販薬としても販売されています。その中でもセラミドやヒアルロン酸等が入っている保湿剤は市販薬にしかありません。その時の用途に合わせて選んでみましょう。